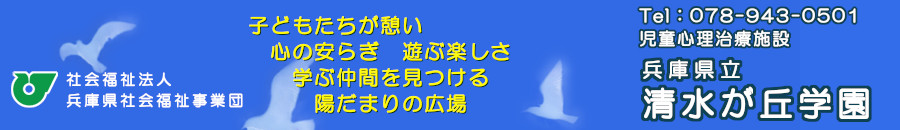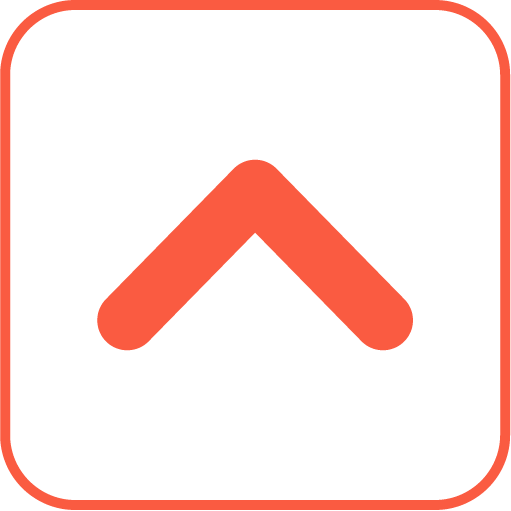運営方針
基本方針
- 私たちは、子どもたちの権利を保障します。
- 子どもたちの心を理解し、心を育む生活の場を整えます。
- いかなる暴力からも子どもたちを保護し、すべての子どもたちの権利を尊重します。
- 私たちは、子どもたちの成長・発達を支援します。
- 一人ひとりの子どもの適性や能力が適切に伸びるように支援します。
- 基本的な生活習慣や道徳観を身につけ、発達年齢に相応しい正義感や責任感が持てるよう支援します。
- 様々な年齢の友だちや大人との交流を通じ、「育つ喜び、育ちあう楽しみ」を経験できる環境づくりに取り組みます。
- 私たちは、子どもたちの自立を支援します。
- 子どもたちの発達年齢に応じた学力や生活技術の習得を支援します。
- 子どもたちの能力や希望を尊重した進路選択を支援します。
- すべての子どもたちが自分を大切にし、生き甲斐を実感できるよう支援します。
- 私たちは、家庭や地域の子育てを支援します。
- 子どもの健全な成長を願う保護者の想いを受け止め、協力して子育てを行います。
- 知恵や知識を地域の人々と共有し、より良い子育てのあり方を考えます。
- 学園の機能を地域に還元します。
令和6年度事業計画
清水が丘学園(以下「学園」)は、児童福祉法に基づく「児童心理治療施設」として家庭環境やその他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を入所または通所で受け入れ、支援を行っています。
近年、学園の入所児童は、虐待や発達障害等を複合した課題を抱える児童が中心となっており、トラウマ反応を示すなど対応が難しい児童が増えています。特に愛着の課題をベースにストレス耐性や感情のコントロールが身についておらず、衝動的な行動に至るなどの課題を抱える児童が多くなっており、他機関と連携しながらのより専門的・総合的な取り組みが必要となっています。同時に子どもの問題は、家族が抱える問題に起因することが多く、不調をきたした家族に対する支援も重要となっています。
通所、外来相談においては、家庭生活や学校生活における児童、家族の困りごとに対する相談、支援を行っています。特に不登校対策については、県の「不登校児童生徒への全県応援ネットワーク」の一機関としての役割を担っています。
今年度は、従来の取り組みをより深めるとともに、特に①子どもの権利擁護の推進、②退所児童に対するアフターケアの実施、③職員の専門性の向上、④施設・設備のメンテナンスについて重点的に取り組んで参ります。
以上の方針のもと、令和6年度の事業として、次のとおり計画を定めます。
- 時代に求められる利用者本位の質の高いサービス提供
- (1)子どもの人権と個人の尊厳に配慮したサービスの提供
- ①子どもの権利擁護・被措置児童虐待防止・不適切な支援に関する研修等の実施
- ②権利擁護の推進
- ③外部有識者によるスーパーバイズ(事例検討)の実施
- (2)子どもにとって安全・安心なサービスの提供
- ①あったかサポート運動の実践、ヒヤリハット・事故報告の検証
- ②危機管理基本指針に基づくリスクマネジメント体制の確立
- (3)子ども本位で質の高いサービスの提供
- ①サービス評価基準に基づく自己評価実施
- ②セカンドステップ(暴力防止プログラム)、性教育等の実施
- ③社会体験事業の実施
- ④業務マニュアルの見直し・検討
- (4)子どもの多様な個別ニーズに対応したサービスの提供
- ①個室化の推進
- ②特性に合わせた支援
- (5)心理的ケア等を必要とする子どもやその家族に対する支援の充実
- ①トラウマ関連症状に対するケアの実践
- ②家族療法(外来児童・家族支援)事業の推進
- (6)継続的な支援の提供
- ①アフターケアの実施
- (7)医療・福祉・教育の連携
- ①児童相談所との連携
- ②教育関係機関との連携
- ③医療機関との連携
- ④県立こども発達支援センターとの連携
- 地域共生社会の実現に向けた取組
- (1)施設機能の地域への提供・発信
- ①児童心理臨床セミナーの開催
- ②公開講座の開催
- ③支援ニーズの高い事例検討会や研修会への講師派遣
- ④外来相談の実施
- ⑤電話相談(福祉ダイヤル)の実施
- (2)地域の福祉人材育成支援
- ①公認心理師、臨床心理士臨床実習の受入れ
- ②社会福祉士・保育士・教職員実習の受入れ
- ③見学研修(大学生、民生委員・児童委員等)の受入れ
- ④インターンシップの受入れ
- ⑤児童福祉施設職員研修の受入れ
- (3)地域に開かれた施設運営
- ①ボランティアの受入れ
- ②事業団広報戦略に基づく広報の推進
- ③専門職種連絡会への参加
- 人材の確保・育成・定着と魅力ある職場づくり
- (1)職員の専門性の向上
- ①職員研修の充実
- ②OJTの充実
- ③自己研鑽機会の充実
- ④公認心理師、社会福祉士、介護福祉士等の計画的育成、資格取得の推進
- 持続可能な施設運営
- (1)経営基盤の確立(入所児童の安定的受入れによる措置費収入の確保)
- (2)県とのパートナーシップによる県施策の実践
- (3)施設・設備のメンテナンス
- ①空調設備の更新
- ②屋上の防水補強